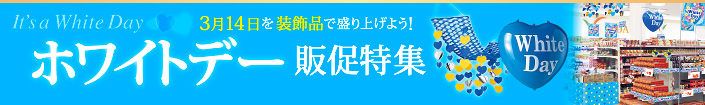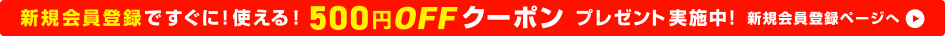【冬のイベントといえば?】 冬の催事・イベントをまとめてみた。

日が落ちるのも早くなってきており、朝が肌寒く感じる日もある今日この頃。
今回は冬に向けて、冬の催事をご紹介いたします。
引き続き、コロナ禍の影響が続いておりますがイベント・催事の参考になれば幸いです。
1.お歳暮(冬の贈り物)
時期:毎年12月中旬から下旬
お歳暮という言葉は、もともとは読んで字の如く年の暮れ、
年末(歳暮=さいぼ・せいぼ)という意味を表わす言葉でした。
毎年、この時期になると一年間にお世話になった人に贈り物を持参してまわる習慣ができ、
これを歳暮回り(せいぼまわり)と言うようになり、
やがて、贈答品そのものを「御歳暮」と呼ぶようになり、現代に至っています。
12月初めより遅くとも20日頃までに贈るのが一般的で、
それを過ぎるようであれば年明けにお年賀として贈ると良いとされています。
また、シーズン終了後に贈答用のギフトセットをばらして割安で販売する「解体セール」は人気があります。
お歳暮の展開には、他の売り場との差別化を図り、高級感のあるデザインで華やかさを演出するのがおすすめです。
赤のビニール幕やポスターで華々しく売り場を彩りましょう!
お歳暮販促品特集はこちら

2.クリスマス
時期:12月25日
冬の一大イベントであるクリスマス。
クリスマスといえば、欠かせないのがクリスマスケーキですよね。
特に定番のケーキといえば、やはりイチゴのショートケーキではないでしょうか。
ですが、クリスマスの本場である欧米諸国ではショートケーキをではなく、別のケーキのほうがメジャーだそうです。
フランスだと有名なのが、「ブッシュ・ド・ノエル」
「クリスマスの丸太」という意味で、ロールケーキをココアクリームでコーティングして装飾を施したケーキですね。
最近のケーキ屋さんではこちらもお勧めすることもあり、日本でも見かけるようになりました。
ドイツやオランダですと、「シュトレン」と呼ばれる伝統菓子が有名です。
ケーキというよりかは、菓子パンに近く、酵母の入った生地に、レーズンやナッツ、オレンジピールやレモンピールを練り込ませ、焼き上げたあとに真っ白になるまで粉砂糖をまぶしたお菓子となります。ドイツでは、クリスマスを待つ「待降節(アドベント)」の間、少しずつ食べる習慣があるそうです。
クリスマスが近づくにつれ、味が熟成され、当日が待ち遠しくなると言われてます。
日本のクリスマスケーキの由来は、スイーツで有名な老舗食品メーカーが、1922年(大正11年)ごろに広めたのがきっかけと言われています。
その時のケーキが、イチゴのショートケーキをサンタの装飾でデコレーションをしたものらしく、今の日本のクリスマスケーキの源流となったと言われています。
クリスマス販促品をお探しの方はこちら

3.お正月(元旦・元日)
時期:1月1日
一年の初めであるお正月。
大晦日に年越しそばを食べて初日の出を楽しんだり、元日から福袋を購入したり、テレビでゆっくり駅伝や特番を見ながら過ごしたりと色々な楽しみ方がある1日ではないでしょうか。
お正月装飾品をお探しの方はこちら

4.節分
時期:2月3日(または2月2日)
1985年から2020年まで節分は毎年2月3日でしたが、
2021年、2025年、2029年は予定ではありますが、2月2日が節分の日になると言われています。
では何故、節分の日が動くのでしょうか?
答えとしては、節分は立春・立夏・立秋・立冬の前の日とされているからです。
立春・立夏・立秋・立冬の日は太陽の位置によって1年を24に分け、それぞれの季節に名前をつける「二十四節気」のうち1日であり、これらの日にちは地球と太陽との位置関係を国立天文台が調べて決められております。
つまり、地球と太陽の位置関係が変われば、節分の日も変わるという仕組みになっております。
2030年以降は予測になりますが、2月2日が節分の日になる年の方が多いと見込まれております。
そのうち、「2月2日が節分の日」という常識になっていくのではないでしょうか。
節分・恵方巻の販促品探しの方はこちら

5.バレンタインデー(ホワイトデー)
バレンタインデーの時期:2月14日(ホワイトデーの時期:3月14日)
平日だとどうしても会社の人に義理チョコやお返しを用意するのが大変…。
「チョコを渡して楽しむ」というイベントから、「親しい人とのランチ・ディナー」であったり「おうちでチョコ作りを楽しむ」などといった「コト消費」にシフトするのではないでしょうか。
バレンタインの装飾品をお探しの方はこちら
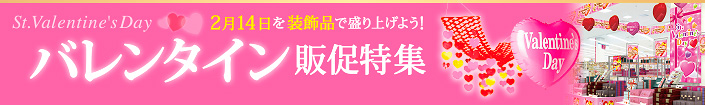
ホワイトデーの装飾品をお探しの方はこちら